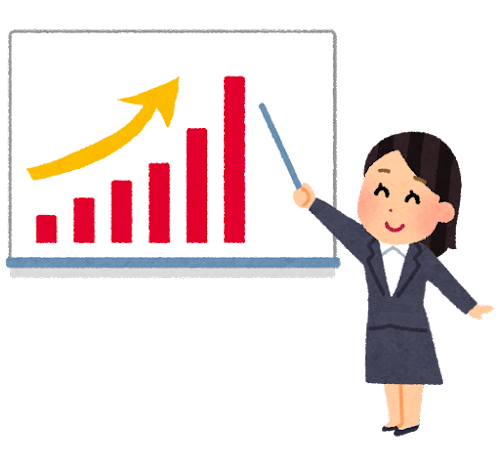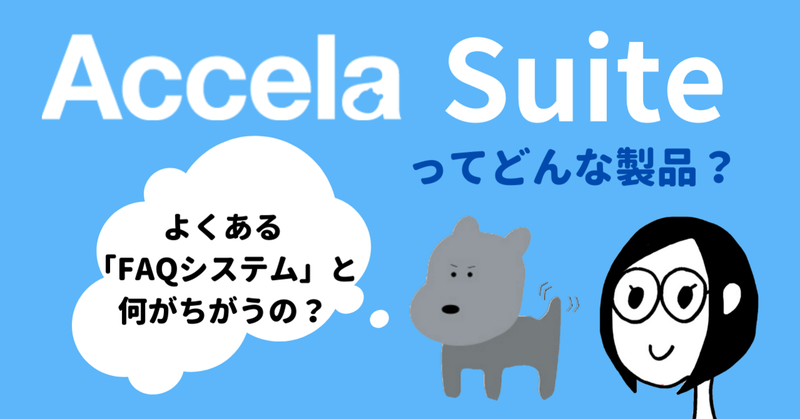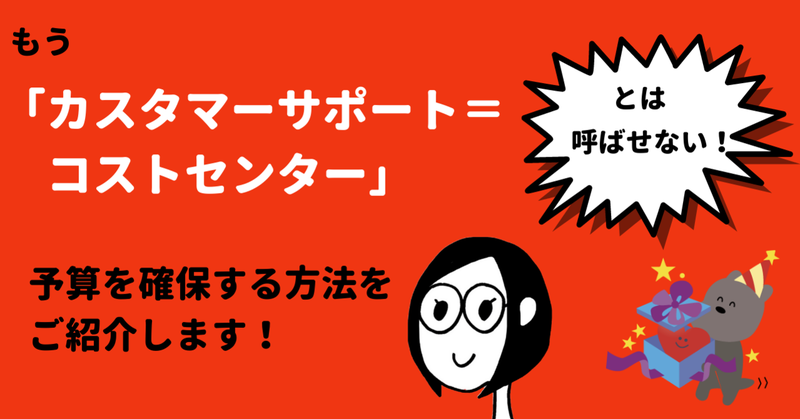
もう「コストセンター」とは呼ばせない!予算を確保する方法をご紹介します!
みなさん、こんにちは!😊
「ひえちゃん」こと、稗田 朱花(ひえだ あやか)です。
今日はわたくしテレワークなのですが、部屋の空気の入れ替えをしようと窓を開けたら…
~~~♪…
どこからともなく、ハーモニカの音色が。なんだろう?とあたりをきょろきょろしてみると、ハーモニカの音が途切れると同時に「すご~い!」と拍手喝采の声。そのあとに、照れくさそうなおじいちゃんが何か嬉しそうに喋っているのが聞こえました。お向かいの家のおじいちゃんが、デイサービスのヘルパーさんたちをお客さんにハーモニカの腕前を披露していたのでした。
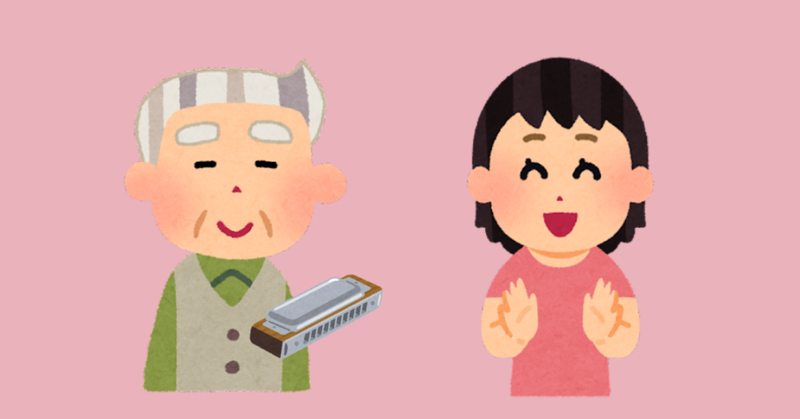
テレワーク、お仕事をする上では大変な場面もありますが、こんな素敵な体験ができるのなら在宅勤務もいいものだなあ…と、しみじみ思ってしまいました😌 バリバリの下町在住、ひえちゃんです!😊
さて、今回のテーマは「もう『コストセンター』とは呼ばせない!」。
気合いたっぷりのタイトルですが…最近巷でよく聞く「コストセンター」という言葉。従来「コストセンター」と呼ばれてきたカスタマーサポートの市場で、今新たな動きが起こっています。
今回はそちらに関して、ナレッジ活用という観点から、わかりやすくご紹介させていただきます!
目次
そもそも「コストセンター」って?
コストセンターとは一般的に、企業内における「コストは集計されるが利益は集計されない部門」を指します。
コールセンターのように、お客様のお問い合わせやクレームへの対応を主とするカスタマーサポートの分野は、従来よりこの「コストセンター」として消極的なイメージを持たれがちでした。

しかし、近年では「お客様と直接つながり貴重な声を収集できる組織の重要な部門」として、カスタマーサポート部門の価値を重視する企業が増えているのです!✨
私が以前にお話させていただいたコールセンターのお客様も「お客様と直接やり取りができて、生の声を他部門に届けられるのがうちの部門のやりがいです!」と仰っていました。(私もそう思います!)

…そうはいっても、コールセンターやサポートセンターだけでの投資効果を考えると、予算確保はなかなか難しい場合もあります。また、会社ごとの予算に対する考え方もあるでしょう。
そこで!
今回は我々アクセラテクノロジが、カスタマーサポート部門で予算を確保するための方法をご提案させていただきます!
方法としては下記の2通りです。
①お客様へ改善提案を行い「プロフィットセンター」化をめざす方法
②他部門を巻き込んだ「ナレッジ活用」で予算確保を行う方法
では、早速その具体的な方法を見ていきましょう!
①お客様へ改善提案を行い「プロフィットセンター」化をめざす!
まず、ひとつめは「お客様へ改善提案を行い「プロフィットセンター」化をめざす」方法です。
プロフィットセンターとは、「直接的に利益に貢献する部門」を意味する言葉であり、コストセンターの対義語にあたります。「直接的に利益に貢献する」とはどういうことか、例を出して考えてみましょう。
たとえば、Wi-Fiルーターに関する問合せのサポートセンターの場合。

オペレーターがお客様から「Wi-Fiの速度が遅い」というトラブルに関する問合せをいただいたとします。ここで原因を調べたときに、それが「キッチンでWi-Fiを使用している」ことに起因していたトラブルだった場合、対応方法としては二通りが考えられるかと思います。
ひとつは、
①「電波の届きにくいキッチンで使用しているのが原因なので、別の場所で使用するようにしてください」
と案内する方法。そしてもうひとつは、
②「それは電波の届きにくいキッチンで使用されているのが原因ですね。もしよろしければ、より広い範囲でお使いいただけるこちらのプランがございまして…」
と、上位のプランへとお客様を誘導する等、お客様へ改善提案を行う方法です。このふたつの対応を見くらべたとき、もし②で上位のプランへとお客様を誘導し契約へつなげられた場合、アップセルが成功して直接的に利益に貢献することになりますよね。そして、もちろん顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
このように、お客様へ改善提案を行って「プロフィットセンター」化を目指し、売上そのものを増加させることで予算を確保する方法が有効です。
②他部門を巻き込んだ「ナレッジ活用」で予算確保!
そして、もうひとつは「他部門を巻き込んだ『ナレッジ活用』で予算確保を行う」方法です。
弊社のとあるお客様を例に出してみましょう。
コールセンターで「Accela Suite」によるナレッジ活用を行いたいと考えておられたこちらのお客様は、そのような用途の予算がセンターになくてどうしよう…と考えた末に、他の部門を巻き込み、複数部署で予算を集めて導入されました。
これは単に「予算」だけでの話ではなく、ナレッジの活用の観点からは大変理にかなっている導入法なんです。
なぜかというと…ちょっと一緒に考えてみましょう🤔
ナレッジを参照するのはあくまでコールセンターのオペレーターです。
でも、そのナレッジのもととなる、技術的、あるいは専門的なノウハウはどこが用意するのでしょうか?
多くの場合は、製品やサービスの責任部門が、保守マニュアルやサポート手引きのような形で用意すると思います。ナレッジの活用と創出の観点から考えれば、当然複数の部門にまたがるものです。
コールセンターでナレッジの活用が進めば問題解決率は高くなり、製品部門へのエスカレーションは確実に減ってきます。それによって、両方の部門が恩恵を得ることができます。
さらに、
「この機能がよく壊れる」
「このマニュアルの表記が誤解をうむ」
など、カスタマーサポートの現場ならではの「気づき」が、ナレッジベースを介してコールセンター側から製品部門側に伝えられることで、製品やマニュアルそのものの改善にもつなげられます。
つまり、この「他部門を巻き込んだ『ナレッジ活用』」で自社への改善提案を行うことで、直接的に会社の利益に貢献し「プロフィットセンター」化につなげることができるのです!
是非、このような活用イメージを念頭に、予算確保を行うことをおすすめいたします!😊
必聴!「攻めのコールセンターセミナー」開催!
いかがでしたでしょうか?
ここまで「コストセンター」を「プロフィットセンター」化させることで予算を確保する方法をご提案させていただきました。
でも、こちらでご紹介した内容だけだとなかなか実運用までのプロセスがつかみにくいですし、じゃあ具体的にはどうすればいいの?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
そこで!
なんと、今回ご紹介させていただいた内容を、お客様事例を交えてわかりやすくご紹介させていただく、その名も『攻めのコールセンター』セミナー」を、アクセラテクノロジが開催させていただきます!🔥
※Webセミナーですので、どちらからでもご参加いただけます!
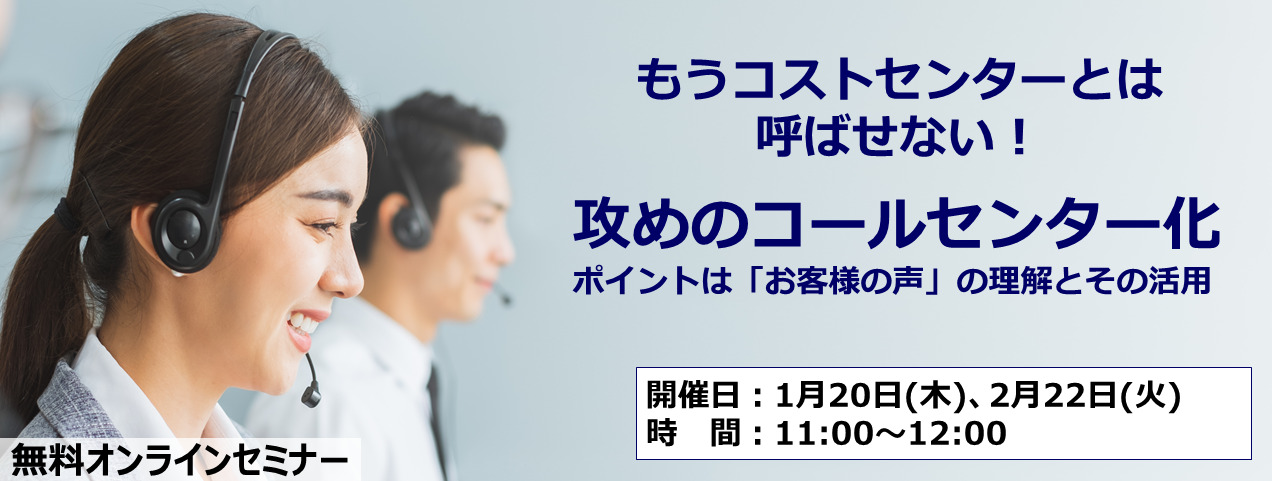
※お申込みの際に、自由ご記入欄に「記事見たよ!」と一言ご記入いただけますと泣いて喜びます😭✨
皆さまのご参加を、心よりお待ち申し上げております!
ここまでご覧いただき、ありがとうございました😊
次回の記事も、どうぞお楽しみに!
- ナレッジネット (1)
- WebRAG (2)
- チケット (1)
- ARG (7)
- DAG (7)
- ドリルダウンRAG (10)
- チャットボット (3)
- Web (3)
- テクニカルサポート (3)
- RAG (1)
- AI (19)
- ナレッジ×AI活用導入事例 (1)
- マスターナレッジ (1)
- となりの営業マン (4)
- ナレッジ活用導入事例 (3)
- グローバル展開 (1)
- 活用シーン (1)
- カスタマーサクセス (2)
- サプライチェーン (1)
- Accela BizAntenna (2)
- 多言語間ナレッジ共有 (2)
- 脱属人化 (1)
- 新機能 (1)
- 添付ファイル翻訳機能 (1)
- アクティブフォーム (1)
- 超サービスデスク (2)
- SolutionDesk (29)
- ヘルプデスク (1)
- 自動翻訳 (3)
- Accela Suite (8)
- ペーパーレス (1)
- 電子化 (1)
- PoC (1)
- 海外連携 (4)
- 未然防止 (1)
- 製造業 (7)
- 暗黙知・形式知 (1)
- 技術・技能伝承 (2)
- ナレッジの動脈と静脈 (1)
- キュレーター (1)
- コールセンター (10)
- カスタマーサービス (1)
- コミュニケーション (2)
- カスタマーサポート (20)
- DX (3)
- SECIスパイラル (2)
- SECIモデル (9)
- SECI実践の話 (6)
- 超FAQ (7)
- FAQ (6)
- 業務改善 (2)
- ナレッジベース (1)
- ナレッジマネジメント (46)